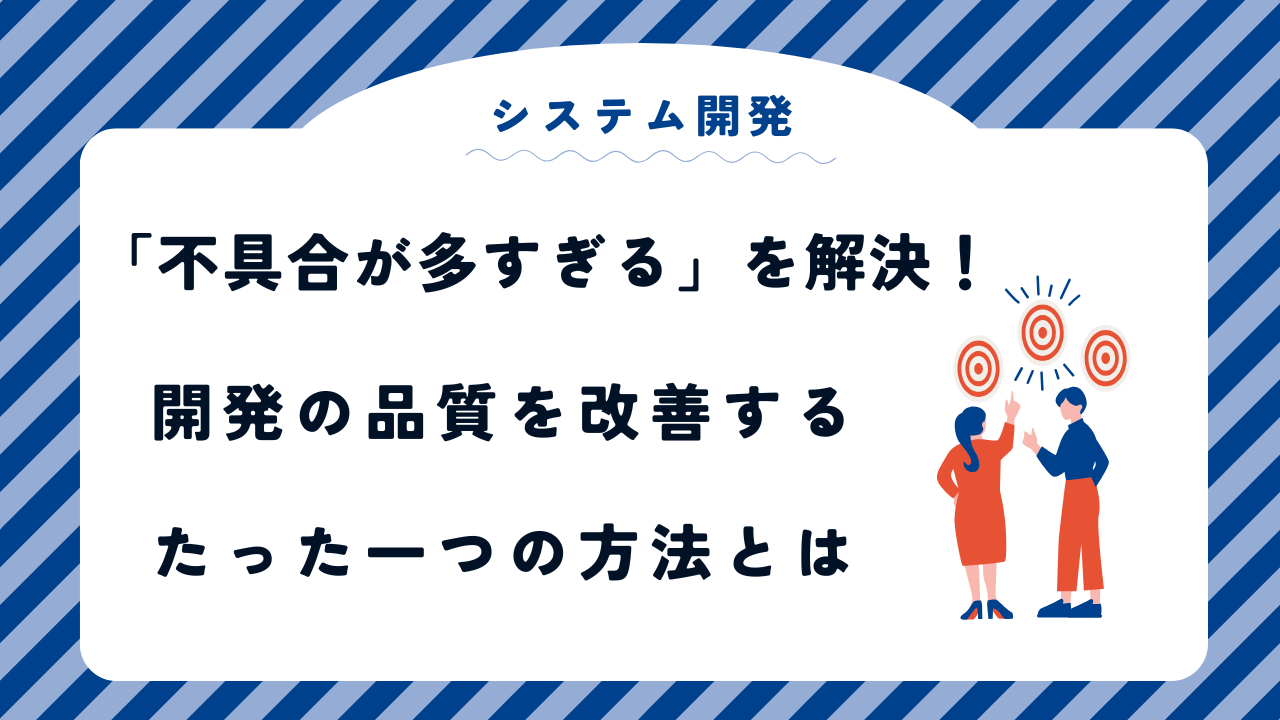「システム開発に多くの費用を注ぎ込んだのに、不具合が多すぎる」
「あれだけ納期を調整したのに、調整後の納期でも間に合わない」
「ベンダーには、人手が足りないからと追加費用を要求される」
当社にご相談いただく企業の多くも、システム開発におけるQCD*の悪さに同じような悩みを抱えています。
これらのトラブルの原因は、実は人手不足そのものではありません。
本当の問題は、「限られた人や時間、お金を、どこにどう使うか」というバランスがうまく取れていないことにあります。
今回は、上記のような課題を抱えていた事業会社A社の改善事例を紹介します。
*QCD:Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)の頭文字を並べたもの。この3要素は相互に関係して成り立っており、バランスや優先順位を考えながら業務に取り組むことが重要である。
参考:キーエンス「業務改善に役立つ「QCD」とは?優先順位やバランスのとり方を解説」
A社の状況
A社は、自社商品の販売強化のためにオンラインショップの開発を大手システム開発ベンダーに委託していました。
事業戦略に直結する重要なプロジェクトとして、予算もスケジュールも余裕をもって開始したはずでしたが———
プロジェクトはたびたび遅延し、リリース予定日が何度も後ろ倒しに。
ようやくリリースに漕ぎつけたと思えば、決済エラーや在庫表示の不具合が多発し、顧客対応に追われる事態に。
そのたびにベンダーからは「人手が足りません」と説明され、A社は追加の費用を支払って対応を依頼してきました。
しかし、どれだけお金をかけても状況は変わりませんでした。
なぜこのプロジェクトはうまくいかないのか。
そもそも何がシステム開発の問題なのかも分からない———
そんな行き詰まりを感じていたタイミングで、当社にご相談をいただきました。
当社が行ったQCD改善の取り組み
当社が最初に取り組んだのは、A社が蓄積してきた社内の資料の定量的な分析でした。
日々の開発で作成されていた不具合報告書や試験関連のドキュメント、会議資料や設計書をデータ分析やAI解析にかけると、それほど重要ではない作業に多くの時間やお金がかかっていた一方、品質を左右する作業にはあまり手が回っていないという現状が見えてきました。
そこで当社は、「どの作業にどれだけ力を入れるべきか」を整理し、人手やお金をかける場所を見直す提案を行いました。
※実際の提案資料(機密情報保護のため加工しています)

こうした分析と改善を一度きりではなく、何度も繰り返すことで、A社は「なぜこの費用が必要なのか」「どこに力を入れれば良いのか」を理解しながら納得感を持って開発を依頼できる状態へと変わり続けており、この取り組みは他の部署にも伝わり、全社的に「限られた時間・お金をどう使うか」を見直す動きが広がっていきました。
また、効率化により余った予算は新規事業などの新しい試みを行う予算へと投資され、社内が攻めの姿勢へと変わっていくこととなりました。
QCD改善の鍵は”社内資料”にあり
この事例から見えてくるのは、システム開発のQCDが悪化する本当の原因は、単なる人手不足ではないということです。
むしろ問題は、「人やお金をどこにどう配分するか」が見えていないことにあります。
そしてその答えは、日々のシステム開発で生まれる社内資料をもとに定量的に読み解くことができるのです。
「なぜか開発がうまくいかない」と感じたら、まずはご相談ください
「QCDが悪いが、どこを改善すればいいのか分からない」
「エンジニアはたくさん残業をしているが、不具合が減らない」
「品質を上げるためにはより多くの費用を請求される」
こうしたお悩みがある場合、まずは社内資料の定量的な分析を行うことで、改善のきっかけが見えてくるかもしれません。
なお当社では、システム開発のQCDの原因を分析する初期診断を実施しています。
「うちも似た状況かもしれない」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
ご相談はこちら